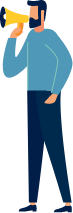このコーナーでは、「わたしたちのくらしと生命保険」をテーマにした公益財団法人生命保険文化センター主催による第61回中学生作文コンクールの入賞作品をご紹介します。

福岡県 東福岡自彊館中学校
三学年 清武 琳(きよたけ りん)
生後二週間目に障害があると診断されたその時から、僕と家族の闘病生活が始まった。
僕は脊柱側弯症と肋骨欠損という、なかなか重めの障害を持って生まれてきた。
両親は医師から、五歳になったら手術を始めること、その後は半年に一度の手術が必要なことなどを告げられた。
そろって楽天的な両親は、一瞬絶望的な気分になったものの、こんな体でも生まれてくるなんて、きっと生命力の強い子に違いないから大丈夫だ、と思ったそうだ。
僕は障害のために発育が遅く、母は乳幼児健診に行くのが苦痛だった。同じ月齢の子が歩いているのに、我が子は座ることさえできないのだから当然だ。
ある日父は職場で学資準備のための保険を勧められた。熱心に勧誘していたその人は、父が僕の体の話をしたとたんに、あっさり引き下がった。父は僕の保険については考えたことがなかったので、その時ようやく、我が子は保険に入れないかもしれないという不安を感じた。
同時に、当たり前だと思っていた生命保険への加入が、日々の生活を送る中で、実はとても大きな安心材料になっていたことに初めて気づいた、と話してくれた。
その後、母の叔母の紹介で、僕も保険に入ることができた。もちろん側弯の入院手術は対象外だが、その他の病気やケガで治療を受ける時はカバーしてもらえる。
僕はこれまでに十八回手術を受けた。手術費用の総額は三千万円以上になる。
ありがたいことに、子どもは病気になっても、高額の医療費を支払う必要はない。ただ、入院すると病院から付き添いを求められることがある。
幸い母は僕の入院付き添い中、有給休暇を取ることができる。入院の日程は事前に決まっているから準備もできる。でも、急に子どもの入院が決まり、困っているお母さんたちもたくさんいた。
付き添い中は仕事に行けない。自宅が遠く、面会の度に新幹線で通ってくる家族もいた。幼い弟妹がいれば、その子たちの世話をする人も必要だ。付き添いのために退職や転居をした人も多い。
子ども一人が入院すると、家族全員に大きな負担がかかる。体力的にも、精神的にも、経済的にも。
昨年、コロナ禍での入院付き添いの過酷さが報じられ、闘病中の子どもに付き添う親を支援する制度がないことが問題視された。
医療費はかからなくても、付き添う親が働けないために、収入が減ってしまう家庭もある。たとえ子どもでも、誰がいつ病気になるかはわからない。
突然やってくるかもしれない「その時」に備え、自分と家族を守るために準備をする。それが保険に加入する、ということなのだと思う。
僕は昨年、新型コロナウイルスに感染した。母は入院給付金の申請のため、初めて保険会社に電話をかけた。
ガチガチに緊張していた母は、僕の体調を気遣ってくれる担当の方の優しい言葉に、涙が出るほど安心したそうだ。これから先、もし何かあっても、保険に助けてもらっていいのだと実感した、と話していた。
子どもが病気で苦しむ姿を見れば、親は自分のことなど大変だと思う余裕すらない、と母は言う。
保険はお守り、というが、それは単なる気休めではない。助けてと声を上げることさえできないほど困った時に救ってくれる、現実的で確実なお守りなのだ。
僕が大人になる頃には、いろいろなことが今とは変わっているかもしれない。でも、どんなに医学が進歩しても、病気やケガはなくならないし、命はやがて尽きる。不意に「その時」が訪れることもあるだろう。
事故、難病、障害、入院、手術、死。自分には関係ないと思いたいし、つい目を背けたくなる。けれど、だからといって事前に備えておかなければ、「その時」が来てからでは遅いのだ。
障害があって良かったと思ったことなど一度もない。だけど、こんな体で生まれたからこそ見えるものがあり、わかったことがたくさんある。
障害があっても、病気になっても、安心して生きていける。この国に生まれたことを、僕は心から幸せだと思っている。