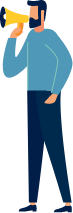日々の生活に根ざした定番料理の歴史やルーツを探る「ごちそうの歴史」。前回ご紹介した「かき氷」に続いて今回取り上げるのは「天ぷら」。数百年前に伝来した南蛮料理を起源とし、300余年の時を経て独自の発展を遂げた日本料理の代表格です。
 出会いのきっかけは南蛮貿易
出会いのきっかけは南蛮貿易
サクッと心地よい食感の衣が、旬の魚介類や野菜のおいしさを引き立てる「天ぷら」。寿司、すき焼き、ラーメンなどと並んで世界的な知名度を誇る日本料理のひとつですが、その起源は安土桃山時代にまでさかのぼります。
16世紀後半に南蛮貿易が始まると、貿易の拠点である長崎にはポルトガルの宣教師によってさまざまな知識や文化が流入しました。そのひとつが天ぷらのルーツである、魚や野菜に衣をつけて揚げる南蛮料理。ただし、この揚げ物は現在の天ぷらとは異なり、衣自体に塩、砂糖、酒などでしっかりと味がついており、つゆも塩もつけずにそのまま食べるのが特徴。食感もふんわりと柔らかで、フリッターのような料理でした。
食用油が貴重な時代においてこの料理が庶民の口に入ることはほとんどありませんでしたが、レシピと文化は長崎の地に根付き、郷土料理「長崎天ぷら」として今も広く親しまれています。
ちなみに、「天ぷら」の語源については今も定かではありませんが、ポルトガル語で調理や味付けを意味する「テンペロ」や、魚や野菜を揚げて食べる習慣があったキリスト教の斎日「テンポラ」などから転じたと考えられています。
 上方文化を経て江戸の名物に
上方文化を経て江戸の名物に

■「たね七分 腕三分」の料理といわれる天ぷら。食材の良し悪しが味を左右する。
17世紀に入ると、長崎天ぷらは京都・大阪などの上方文化圏に伝来。衣にはあまり味をつけず、主に野菜などの非動物性の食材を使い、だしや塩をつけて食べるなど、上方の食文化を反映して発展を遂げました。上方ではこの料理は衣をつけて揚げることから「つけ揚げ」と呼び、衣をつけずに魚のすり身を揚げた、いわゆる「さつま揚げ」を「てんぷら」と呼んでいました。この名称は今でも西日本を中心に定着しています。
やがて、食用油の生産量が増えてきたことで庶民でも揚げ物が食べられるようになり、長崎に伝わって上方で発展した天ぷらは、江戸幕府が開府して間もなく江戸に伝来。日本橋川沿いにできた魚河岸の近くで、魚介類に衣をつけて揚げる立ち食い屋台が登場しました。
江戸の天ぷらは衣にはほとんど味がついておらず、揚げたてを串に刺して提供し、天つゆをつけて食べるというファストフード感覚の食べ物でした。揚げ油には主にごま油を使用していたため当初は「ごま揚げ」という名前で呼ばれており、次第に天ぷらの名称が一般化。初めの頃は江戸前の魚を使ったものだけを天ぷらと呼び、野菜などを揚げたものは「あげもの」などと呼ばれて区別されていましたが、次第にその境界があいまいに。いつしか具材を問わず天ぷらと呼ばれるようになり、天ぷらは江戸の郷土料理「江戸前天ぷら」として全国に知られる名物になりました。
 豪華であり大衆的でもある天ぷら
豪華であり大衆的でもある天ぷら

■ 巻物に描かれた江戸時代の生活文化の様子。左から天ぷら屋、するめ屋、四文屋の屋台。鍬形蕙斎「近世職人尽絵詞」
江戸時代において天ぷらは寿司、うなぎ、そばと並ぶ人気の屋台料理でしたが、幕末から明治時代にかけて、天ぷら料理の専門店や料亭など店舗を構える職人が現れ始めました。また、衣にそば粉や卵黄を多く加えて椿油で揚げた「金ぷら」や、卵白を使って白く仕上げた「銀ぷら」なども誕生し、揚げる素材や油の種類を厳選するなど調理法も洗練。さらに、材料や道具を持ち込んで客の前で天ぷらを揚げる出前スタイルの「出揚げ天ぷら」や、小さな座敷天ぷらを提供する「お座敷天ぷら」なども登場し、天ぷらは庶民の料理であると同時に高級料理としての地位も確立されていきました。
しかし、1923年に関東大震災が発生し、地震、火災、津波により多くの建物が倒壊。東京の天ぷら店も甚大な被害を受けますが、職を失った天ぷら職人が日本各地に移り住んだことで江戸前天ぷらの技法が全国に伝わり、東西の交流によって上方ならではの塩をつける食べ方が東京に伝わったと考えられています。
その後、太平洋戦時下においては食料不足のため天ぷらはめったに食べられないごちそうになりますが、戦後の高度経済成長や食用油の生産量増加に伴い家庭でも手軽に揚げ物が作れるようになり、庶民の料理としての天ぷらが復活。また、1989年には熟練した職人がいなくても天ぷらが作れるオートフライヤーを導入した天ぷら・天丼チェーン店が開業。外食でもおいしい天ぷらを低価格で味わえるようになったのです。